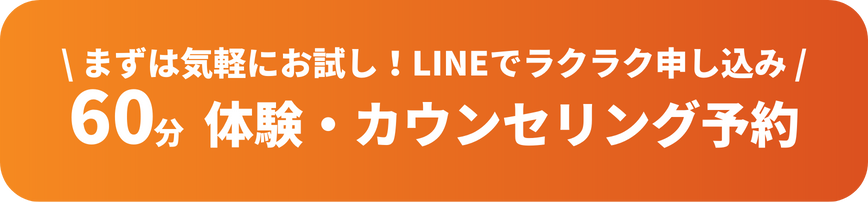「仕事でイライラすると、ついつい甘いものに手が伸びてしまう」
「大事なプレゼンの前になると全く食欲がわかなくなる」
このような経験はありませんか?
実は、ストレスが食欲に与える影響は、私たちが思っている以上に深刻で複雑です。
厚生労働省の調査によると現代人の多くがストレスによる食生活の乱れを経験しており、特に働く世代では「ストレス食い」や「食欲不振」が大きな健康課題となっています。
健康面だけでなくダイエットをしている多くの方もストレスによる食生活の乱れに悩まされています。
ストレスと食欲の関係は、単なる気持ちの問題ではありません。
私たちの脳や体内で起こる生理学的な変化が食欲を大きく左右しているのです。
しかし、そのメカニズムを正しく理解し適切な対策を実践することで、ストレスと食欲の悪循環から抜け出すことは十分に可能です。
そこで今回は、ストレスが食欲に影響を与える科学的なメカニズムから今日から実践できる具体的な対策法まで医学的根拠に基づいて詳しく解説します。
「なぜストレスで食べ過ぎてしまうのか」「どうしたらストレス食いをコントロールできるのか」といった疑問にお答えし、あなたが健康的な食生活を取り戻すお手伝いをいたします。
ストレスが食欲に与える2つの影響とは?

ストレスが食欲に与える影響は、大きく分けて2つのパターンがあります。
✔︎ストレスが食欲に与える影響
- ストレスによる食欲増進
- ストレスによる食欲不振
同じストレスでも人によって、または状況によって正反対の反応が現れることがあるのです。
どちらのパターンも体の正常な反応であり、適切に対処すれば改善できるということです。
ストレスによる食欲増進

多くの人が経験するのが、ストレスによる食欲の増進です。
特に慢性的なストレスを感じている時に起こりやすく普段よりも多く食べてしまったり、特定の食べ物への欲求が強くなったりします。
典型的なストレス食い
- イライラした時に無意識に食べ物に手が伸びる
- 甘いものや脂っこいものが無性に食べたくなる
- 夜遅くにドカ食いしてしまう
- 満腹でも食べ続けてしまう
仕事のプレッシャーや人間関係のトラブル、睡眠不足などが続くと、チョコレートやスナック菓子、ファストフードなど、高カロリーで満足感の得やすい食品を求める傾向が強くなります。
ダイエットの食事制限が強いストレスに感じる方も高カロリーで満足感の得やすい食品を求める傾向が強くなります。
ストレスによる食欲不振

ストレスでの食欲への影響は食欲増進だけでなく、ストレスが食欲を抑制することもあります。
これは主に急性ストレス(短期間の強いストレス)の場合に起こりやすい反応です。
ストレスによる食欲不振
- 大事な会議やプレゼンの前に食事が喉を通らない
- 心配事があると胃がキュッと縮む感じがする
- 普段好きな食べ物でも美味しく感じない
- 食べようとすると吐き気を感じる
このような食欲不振は、体が「戦うか逃げるか」の緊急モードに入った時の自然な反応です。
しかし、この状態が長期間続くと栄養不足による体力低下や免疫機能の低下、代謝の低下さらには新たなストレスの原因となってしまう可能性があります。
ストレスによる食欲不振で食べない状態が続くと一時的に痩せていきますが、筋肉量が減って代謝の低下に繋がるので食欲が戻ったり、ストレス食いnに陥った時に痩せた以上に太る可能性が高いです。

多くの人が経験するのが、ストレスによる食欲の増進です。
特に慢性的なストレスを感じている時に起こりやすく普段よりも多く食べてしまったり、特定の食べ物への欲求が強くなったりします。
典型的なストレス食い
- イライラした時に無意識に食べ物に手が伸びる
- 甘いものや脂っこいものが無性に食べたくなる
- 夜遅くにドカ食いしてしまう
- 満腹でも食べ続けてしまう
仕事のプレッシャーや人間関係のトラブル、睡眠不足などが続くと、チョコレートやスナック菓子、ファストフードなど、高カロリーで満足感の得やすい食品を求める傾向が強くなります。
ダイエットの食事制限が強いストレスに感じる方も高カロリーで満足感の得やすい食品を求める傾向が強くなります。
ストレスによる食欲不振

ストレスでの食欲への影響は食欲増進だけでなく、ストレスが食欲を抑制することもあります。
これは主に急性ストレス(短期間の強いストレス)の場合に起こりやすい反応です。
ストレスによる食欲不振
- 大事な会議やプレゼンの前に食事が喉を通らない
- 心配事があると胃がキュッと縮む感じがする
- 普段好きな食べ物でも美味しく感じない
- 食べようとすると吐き気を感じる
このような食欲不振は、体が「戦うか逃げるか」の緊急モードに入った時の自然な反応です。
しかし、この状態が長期間続くと栄養不足による体力低下や免疫機能の低下、代謝の低下さらには新たなストレスの原因となってしまう可能性があります。
ストレスによる食欲不振で食べない状態が続くと一時的に痩せていきますが、筋肉量が減って代謝の低下に繋がるので食欲が戻ったり、ストレス食いnに陥った時に痩せた以上に太る可能性が高いです。

ストレスでの食欲への影響は食欲増進だけでなく、ストレスが食欲を抑制することもあります。
これは主に急性ストレス(短期間の強いストレス)の場合に起こりやすい反応です。
ストレスによる食欲不振
- 大事な会議やプレゼンの前に食事が喉を通らない
- 心配事があると胃がキュッと縮む感じがする
- 普段好きな食べ物でも美味しく感じない
- 食べようとすると吐き気を感じる
このような食欲不振は、体が「戦うか逃げるか」の緊急モードに入った時の自然な反応です。
しかし、この状態が長期間続くと栄養不足による体力低下や免疫機能の低下、代謝の低下さらには新たなストレスの原因となってしまう可能性があります。
ストレスによる食欲不振で食べない状態が続くと一時的に痩せていきますが、筋肉量が減って代謝の低下に繋がるので食欲が戻ったり、ストレス食いnに陥った時に痩せた以上に太る可能性が高いです。
ストレスと食欲のメカニズムとは?

ストレスによって食欲が変化するのは、私たちの体内で複雑な生理学的変化が起こっているためです。
✔︎ストレスと食欲のメカニズム
- 脳の食欲調節システム
- ストレスホルモン「コルチゾール」の影響
- 神経伝達物質の変化
- 自律神経系の影響
これらの複雑なメカニズムが絡み合ってストレスによる食欲の変化が起こります。
メカニズムを理解することで、なぜ自分の食欲がコントロールできないのかが明確になり適切な対策を立てることができるようになります。
脳の食欲調節システム

私たちの食欲は、主に脳の視床下部という部分でコントロールされています。視床下部には「摂食中枢」と「満腹中枢」という2つの重要な機能があり、これらが協力してバランスよく食欲を調節しています。
摂食中枢は「食べなさい」という信号を送り、満腹中枢は「もう十分食べたから止めなさい」という信号を送ります。
通常の状態では、血糖値の変化や胃の膨張感、各種ホルモンの分泌量などの情報をもとに、この2つの中枢が適切に働いて食欲をコントロールしています。
しかし、ストレスがかかると、この精密な調節システムが乱れてしまいます。特に、レプチンという満腹中枢に働きかけ、食べ過ぎを防ぐホルモンの働きが悪くなり、本来なら「お腹いっぱい」と感じるべきタイミングで満腹感を得られなくなってしまうのです。
ストレスホルモン「コルチゾール」の影響

ストレスを感じると副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、本来は危険な状況に対処するための重要な役割を担っています。
しかし、慢性的なストレス状態でコルチゾールが過剰に分泌されると様々な問題が起こります。
コルチゾールが過剰に分泌による問題
- 血糖値の上昇
- 脂肪蓄積の促進
- 食欲調節機能の混乱
①血糖値の上昇

私たちの食欲は、主に脳の視床下部という部分でコントロールされています。視床下部には「摂食中枢」と「満腹中枢」という2つの重要な機能があり、これらが協力してバランスよく食欲を調節しています。
摂食中枢は「食べなさい」という信号を送り、満腹中枢は「もう十分食べたから止めなさい」という信号を送ります。
通常の状態では、血糖値の変化や胃の膨張感、各種ホルモンの分泌量などの情報をもとに、この2つの中枢が適切に働いて食欲をコントロールしています。
しかし、ストレスがかかると、この精密な調節システムが乱れてしまいます。特に、レプチンという満腹中枢に働きかけ、食べ過ぎを防ぐホルモンの働きが悪くなり、本来なら「お腹いっぱい」と感じるべきタイミングで満腹感を得られなくなってしまうのです。
ストレスホルモン「コルチゾール」の影響

ストレスを感じると副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、本来は危険な状況に対処するための重要な役割を担っています。
しかし、慢性的なストレス状態でコルチゾールが過剰に分泌されると様々な問題が起こります。
コルチゾールが過剰に分泌による問題
- 血糖値の上昇
- 脂肪蓄積の促進
- 食欲調節機能の混乱
①血糖値の上昇

ストレスを感じると副腎からコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは「ストレスホルモン」とも呼ばれ、本来は危険な状況に対処するための重要な役割を担っています。
しかし、慢性的なストレス状態でコルチゾールが過剰に分泌されると様々な問題が起こります。
コルチゾールが過剰に分泌による問題
- 血糖値の上昇
- 脂肪蓄積の促進
- 食欲調節機能の混乱
①血糖値の上昇
コルチゾールは肝臓でのブドウ糖生成を促進し、血糖値を上昇させます。
すると、インスリンが大量に分泌されて血糖値が急激に下がり再び強い空腹感を感じるという悪循環に陥ります。
②脂肪蓄積の促進
コルチゾールは特に内臓脂肪の蓄積を促進します。
これは、ストレス時にエネルギーを確保しようとする体の防御反応ですが現代社会では肥満の原因となってしまいます。
内臓脂肪の蓄積は、生活習慣病のリスクが高くなってしまうので注意が必要です。
③食欲調節機能の混乱
長期間のコルチゾール分泌は、視床下部の食欲調節機能を直接的に障害し適切な満腹感を得にくくしてしまいます。
神経伝達物質の変化

ストレス状態では、脳内の神経伝達物質のバランスも大きく変化します。
急性ストレス時には、ノルアドレナリンという神経伝達物質が大量に分泌され交感神経が優位になり、一時的に食欲が抑制され「緊張すると食欲がなくなる」と言うメカニズムになります。
また、慢性的なストレスは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を減少させます。
セロトニンは満腹中枢の働きを正常に保つ重要な役割があるため不足すると食欲のコントロールが困難になります。
セロトニン不足を補うために甘いものへの欲求が強くなることも知られています。
自律神経系の影響

ストレス状態では、脳内の神経伝達物質のバランスも大きく変化します。
急性ストレス時には、ノルアドレナリンという神経伝達物質が大量に分泌され交感神経が優位になり、一時的に食欲が抑制され「緊張すると食欲がなくなる」と言うメカニズムになります。
また、慢性的なストレスは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を減少させます。
セロトニンは満腹中枢の働きを正常に保つ重要な役割があるため不足すると食欲のコントロールが困難になります。
セロトニン不足を補うために甘いものへの欲求が強くなることも知られています。
自律神経系の影響
私たちの体は、自律神経系によって無意識下でコントロールされています。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、このバランスが食欲に大きな影響を与えます。
ストレスにより交感神経が優位になると胃腸の働きが抑制され、食欲が低下します。
これは体が「今は食べている場合ではない」と判断している状態です。
しかし、ストレスが解放されて副交感神経が優位になると今度は反動で強い食欲が現れることがあります。
これが「ストレス解消後のドカ食い」の正体です。
健康的な食欲を維持するためには、この自律神経のバランスを整えることが極めて重要です。
規則正しい生活リズムや適度な運動、リラックス時間の確保などが効果的とされています。
関連記事
ストレス食いを防ぐ6つの方法

ストレス食いを効果的に防ぐための具体的な対策法をご紹介します。
✔︎ストレス食いを防ぐ7つの方法
- 血糖値の安定化
- ストレス解消の代替手段
- セロトニン分泌を促す習慣
- 食事環境の改善
- 睡眠の質改善
- 適度な運動習慣
これら6つの対策を全て一度に始める必要はありません。
まずは自分にとって取り組みやすそうなものを1〜2個選んで、2週間継続してみてください。
血糖値の安定化

ストレス食いの根本原因の一つは、血糖値の急激な変動です。
血糖値を安定させることで、異常な食欲を抑制できます。
血糖値を安定させる方法
- 低GI食品の活用
- 食事のタイミングと回数の調整
- 食事の順番を意識する
①低GI食品の活用

ストレス食いの根本原因の一つは、血糖値の急激な変動です。
血糖値を安定させることで、異常な食欲を抑制できます。
血糖値を安定させる方法
- 低GI食品の活用
- 食事のタイミングと回数の調整
- 食事の順番を意識する
①低GI食品の活用
GI値(グリセミック・インデックス)は、食品が血糖値をどれくらい早く、どの程度上昇させる指標を示す指標です。
GI値の低い食品を選ぶことで、血糖値の急上昇を防げます。白米の代わりに玄米や雑穀米を、白いパンの代わりに全粒粉パンを選ぶだけでも効果があります。
②食事のタイミングと回数の調整
1日3食を規則正しく摂り、間食は適度に取り入れることは、血糖値を安定させる為に重要です。
長時間の空腹は血糖値の急下降を招き、その後の反動でドカ食いを引き起こします。
空腹時は我慢しすぎず軽い間食(ナッツ類やヨーグルトなど)を摂ることで、夕方以降の食べ過ぎを防げます。
③食事の順番を意識する
食事の内容とタイミングだけでなく食事の順番も血糖値を安定させる為に重要です。
野菜→タンパク質→炭水化物の順番で食べることで血糖値の上昇を緩やかにできます。
この「ベジファースト」は糖尿病予防の観点からも推奨されている方法です。
ストレス解消の代替手段

食べること以外でストレスを発散する方法を身につけることで、ストレス食いの根本的な解決につながります。
10分程度の軽いウォーキングでもストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、気分を改善する効果があります。
また、ゆっくり出来る趣味の時間を作り好きな音楽を聴いたり、本を読んだりすることで副交感神経が優位になり、ストレス反応を和らげることができます。
セロトニン分泌を促す習慣

セロトニンの分泌を促進することで満腹中枢の正常な働きを回復し、食欲をコントロールしやすくなります。
朝の日光浴(15-30分程度)は、セロトニンの原料であるトリプトファンからセロトニンへの合成を促進します。
寝起きでカーテンを開けて朝日を浴びる時間を作ったり朝の通勤時に少し遠回りして歩くだけでも効果的です。
また、起床・就寝時刻を一定にし規則正しい生活を送ることで体内時計が整い、セロトニンの分泌リズムも正常化します。
週末も平日との時差を2時間以内に抑えることが理想的です。
食事環境の改善

ストレス食いを防ぐ為には、食事環境の改善すると言う物理的な対策も効果的です。
高カロリーなお菓子やインスタント食品は、手元に届かないようにする為に買い溜めせずナッツ類、ドライフルーツ、ヨーグルト、野菜スティックなどを間食で食べれる環境を作りましょう。
また、スマートフォンのアプリなどで食事内容を記録することで自分の食行動パターンを客観視できます。
特に「いつ」「何を」「どんな気分で」食べたかを記録すると、ストレス食いのトリガーが見えてきます。
睡眠の質改善

睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを大きく乱し、ストレス食いを悪化させるので睡眠の質を改善する事は、ストレス食いを防ぐ為に必要不可欠です。
睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンが減少し食欲を増進するグレリンが増加します。
これにより、翌日の食べ過ぎが起こりやすくなります。
寝室の温度を16-19度に保ち、遮光カーテンで光を遮断することで、深い眠りを得やすくなり寝具の清潔さも睡眠の質に大きく影響します。
就寝2時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避け、入浴やストレッチなどのリラックス活動を寝る前に行えば睡眠の質が高まります。
適度な運動習慣

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。

食べること以外でストレスを発散する方法を身につけることで、ストレス食いの根本的な解決につながります。
10分程度の軽いウォーキングでもストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、気分を改善する効果があります。
また、ゆっくり出来る趣味の時間を作り好きな音楽を聴いたり、本を読んだりすることで副交感神経が優位になり、ストレス反応を和らげることができます。
セロトニン分泌を促す習慣

セロトニンの分泌を促進することで満腹中枢の正常な働きを回復し、食欲をコントロールしやすくなります。
朝の日光浴(15-30分程度)は、セロトニンの原料であるトリプトファンからセロトニンへの合成を促進します。
寝起きでカーテンを開けて朝日を浴びる時間を作ったり朝の通勤時に少し遠回りして歩くだけでも効果的です。
また、起床・就寝時刻を一定にし規則正しい生活を送ることで体内時計が整い、セロトニンの分泌リズムも正常化します。
週末も平日との時差を2時間以内に抑えることが理想的です。
食事環境の改善

ストレス食いを防ぐ為には、食事環境の改善すると言う物理的な対策も効果的です。
高カロリーなお菓子やインスタント食品は、手元に届かないようにする為に買い溜めせずナッツ類、ドライフルーツ、ヨーグルト、野菜スティックなどを間食で食べれる環境を作りましょう。
また、スマートフォンのアプリなどで食事内容を記録することで自分の食行動パターンを客観視できます。
特に「いつ」「何を」「どんな気分で」食べたかを記録すると、ストレス食いのトリガーが見えてきます。
睡眠の質改善

睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを大きく乱し、ストレス食いを悪化させるので睡眠の質を改善する事は、ストレス食いを防ぐ為に必要不可欠です。
睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンが減少し食欲を増進するグレリンが増加します。
これにより、翌日の食べ過ぎが起こりやすくなります。
寝室の温度を16-19度に保ち、遮光カーテンで光を遮断することで、深い眠りを得やすくなり寝具の清潔さも睡眠の質に大きく影響します。
就寝2時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避け、入浴やストレッチなどのリラックス活動を寝る前に行えば睡眠の質が高まります。
適度な運動習慣

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。

セロトニンの分泌を促進することで満腹中枢の正常な働きを回復し、食欲をコントロールしやすくなります。
朝の日光浴(15-30分程度)は、セロトニンの原料であるトリプトファンからセロトニンへの合成を促進します。
寝起きでカーテンを開けて朝日を浴びる時間を作ったり朝の通勤時に少し遠回りして歩くだけでも効果的です。
また、起床・就寝時刻を一定にし規則正しい生活を送ることで体内時計が整い、セロトニンの分泌リズムも正常化します。
週末も平日との時差を2時間以内に抑えることが理想的です。
食事環境の改善

ストレス食いを防ぐ為には、食事環境の改善すると言う物理的な対策も効果的です。
高カロリーなお菓子やインスタント食品は、手元に届かないようにする為に買い溜めせずナッツ類、ドライフルーツ、ヨーグルト、野菜スティックなどを間食で食べれる環境を作りましょう。
また、スマートフォンのアプリなどで食事内容を記録することで自分の食行動パターンを客観視できます。
特に「いつ」「何を」「どんな気分で」食べたかを記録すると、ストレス食いのトリガーが見えてきます。
睡眠の質改善

睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを大きく乱し、ストレス食いを悪化させるので睡眠の質を改善する事は、ストレス食いを防ぐ為に必要不可欠です。
睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンが減少し食欲を増進するグレリンが増加します。
これにより、翌日の食べ過ぎが起こりやすくなります。
寝室の温度を16-19度に保ち、遮光カーテンで光を遮断することで、深い眠りを得やすくなり寝具の清潔さも睡眠の質に大きく影響します。
就寝2時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避け、入浴やストレッチなどのリラックス活動を寝る前に行えば睡眠の質が高まります。
適度な運動習慣

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。

ストレス食いを防ぐ為には、食事環境の改善すると言う物理的な対策も効果的です。
高カロリーなお菓子やインスタント食品は、手元に届かないようにする為に買い溜めせずナッツ類、ドライフルーツ、ヨーグルト、野菜スティックなどを間食で食べれる環境を作りましょう。
また、スマートフォンのアプリなどで食事内容を記録することで自分の食行動パターンを客観視できます。
特に「いつ」「何を」「どんな気分で」食べたかを記録すると、ストレス食いのトリガーが見えてきます。
睡眠の質改善

睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを大きく乱し、ストレス食いを悪化させるので睡眠の質を改善する事は、ストレス食いを防ぐ為に必要不可欠です。
睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンが減少し食欲を増進するグレリンが増加します。
これにより、翌日の食べ過ぎが起こりやすくなります。
寝室の温度を16-19度に保ち、遮光カーテンで光を遮断することで、深い眠りを得やすくなり寝具の清潔さも睡眠の質に大きく影響します。
就寝2時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避け、入浴やストレッチなどのリラックス活動を寝る前に行えば睡眠の質が高まります。
適度な運動習慣

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。

睡眠不足は食欲ホルモンのバランスを大きく乱し、ストレス食いを悪化させるので睡眠の質を改善する事は、ストレス食いを防ぐ為に必要不可欠です。
睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンが減少し食欲を増進するグレリンが増加します。
これにより、翌日の食べ過ぎが起こりやすくなります。
寝室の温度を16-19度に保ち、遮光カーテンで光を遮断することで、深い眠りを得やすくなり寝具の清潔さも睡眠の質に大きく影響します。
就寝2時間前からはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避け、入浴やストレッチなどのリラックス活動を寝る前に行えば睡眠の質が高まります。
適度な運動習慣

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。

有酸素運動を30分行うことでストレスホルモンのコルチゾール濃度が大幅に減少することが研究で示されています。
激しい運動である必要はなく、早歩きや軽いジョギングでも十分効果があります。
また、定期的な運動は、レプチンの働きを改善し満腹感を感じやすくします。
運動直後は一時的に食欲が抑制される「運動性食欲不振」という現象も活用できます。
ストレスで食欲がない時の適切な対処法

ストレス食いとは逆に、ストレスによって食欲が失われてしまうケースも珍しくありません。
食欲不振が続くと、栄養不足による体力低下や免疫機能の低下を招き、さらなるストレスの原因となってしまいます。
また、代謝の低下に繋がり太りやすく痩せにくい体へとなってしまうのでダイエットが大変になります。
ここでは、食欲がない時でも必要な栄養を摂取し健康を維持するための実践的な方法をご紹介します。
少量で食事頻度を増やす

食欲がない時に無理に通常の食事量を摂ろうとすると、かえって食事に対する嫌悪感が強くなってしまいます。
量よりも質と頻度を重視した食事でのアプローチが効果的です。
1回の食事量を通常の半分程度に減らし、その代わりに食事回数を1日5-6回に増やし少ない量でも効率よく栄養を摂取しましょう。
ナッツ類、卵、バナナ、ヨーグルトなどは、小さな量でも高い栄養価の高い食材を選んだり、プロテインを牛乳や豆乳で割って手軽にタンパク質を摂取する事がおすすめです。
温かいスープ類も水分補給と栄養摂取を同時に行えるため効果的です。

食欲がない時に無理に通常の食事量を摂ろうとすると、かえって食事に対する嫌悪感が強くなってしまいます。
量よりも質と頻度を重視した食事でのアプローチが効果的です。
1回の食事量を通常の半分程度に減らし、その代わりに食事回数を1日5-6回に増やし少ない量でも効率よく栄養を摂取しましょう。
ナッツ類、卵、バナナ、ヨーグルトなどは、小さな量でも高い栄養価の高い食材を選んだり、プロテインを牛乳や豆乳で割って手軽にタンパク質を摂取する事がおすすめです。
温かいスープ類も水分補給と栄養摂取を同時に行えるため効果的です。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?
今回は、ストレスと食欲の関係についての解説でした。
ストレスによる食欲の変化は、コルチゾールやセロトニンなどのホルモン、神経伝達物質の変動によって起こる生理学的な現象なので「意志の弱さ」ではなく、誰にでも起こりうる自然な体の反応になります。
生きていると日々、様々なストレスがかかってくるのでストレスを発散したり、ストレスを緩和するなどストレスとの付き合い方も重要ですが、ストレス食いの対策や食欲不振の改善を実践する事も大切です。
ダイエットをしている方の多くもストレスが原因で暴飲暴食したり食事をしっかり摂れないなどの影響が出ることが多いです。
パーソナルジムVIBRUNは、パーソナルトレーニングだけでなく食事指導や生活習慣の改善サポートを受けられます。
マニュアルに沿ったプログラムではなく、お客様1人1人の職業や年齢、性別、体の状態、通う頻度に合わせたプログラムをオーダーメイドで作成するパーソナルジムです。
パーソナルジムをお探しの方は、是非1度パーソナルジムVIBRUNの無料カウンセリング・体験パーソナルトレーニングをお試しください。
パーソナルジムVIBRUNの無料カウンセリングは、トップページのお申込みフォームまたはLINEから受付中です。
パーソナルジムVIBRUNの店舗情報
✔︎パーソナルジムVIBRUN錦糸町・住吉店

| 住所 | 〒135-0001 東京都江東区毛利1丁目11−19 グリーンゲイブルズ 401 |
| 最寄駅 | 住吉駅徒歩2分・錦糸町駅徒歩7分 |
| 営業時間 | 8:30〜22:00 |
✔︎パーソナルジムVIBRUN神田店

| 住所 | 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町6−1 ラッキービル1階 |
| 最寄駅 | 神田駅徒歩4分・岩本町駅徒歩6分 |
| 営業時間 | 9:00〜22:00 |

執筆トレーナー
プロフィール
看護師として4年間病棟で臨床経験を積んだパーソナルトレーナー。
ダイエットやボディメイクが目的でジムに来られた方にも、それ以上のメリットをお伝えして、健康や自分のライフスタイルを考えるきっかけ作ります。
資格・経歴
- 看護師の臨床経験
- 看護師国家資格
- 呼吸療法認定士
- NSCA-CPT